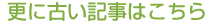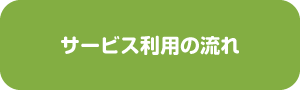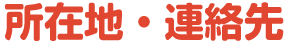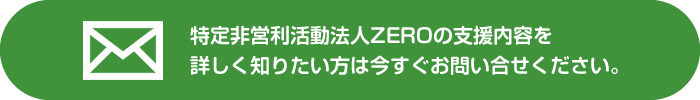生活保護受給者が利用できる就労支援の全知識
2026/01/30
はじめに.
生活保護の受給、就労支援の利用は、併用できます。
どちらが先でも可能ですが、一般的に多いのは、生活保護の申請を完了させてから就労支援を検討するという順番です。
今回は、生活保護を受給しながら就労支援を受ける場合の一般的な流れ、注意点などをまとめました。
生活保護受給者と就労支援の基本
就労支援は、障がいや疾患のある方が無理なく、そして継続的に働くためにさまざまなサポートをする制度です。
就労支援の主な目的は、障がいや病気、個々の特性に応じたサポートを受けながら職業訓練、職場体験など「働くためのスキル、経験」を身につけることです。
就労支援は「働きたいのに制約などにより働けない」状態にあることが利用条件なので、アルバイトはやむを得ない事情がない限り原則として禁止されています。
これは、アルバイトができる状態は「単独での就労が困難である」という就労支援サービスを受ける前提条件と反しているためです。
しかし、預貯金が充分でなかったり、家族からの援助がなかったりすると、就労支援を受けている間の生活に困窮する可能性があります。
そんな時は、生活保護を検討しましょう。
生活保護を受給することで、自立した生活を送ることができるようになります。
生活保護と就労支援(就労移行支援)は、こうした関係にあります。
よって、併用することが可能です。
生活保護制度の目的と、「自立」のための就労支援
生活保護制度の目的は、2つあります。
1つは「健康で文化的な最低限度の生活の保障」です。
2つめは「自立の助長」です。
2025年の生活保護を受給している方の人数は、約200万人です。
リーマンショックや東日本大震災で一時的に増加した時期もありますが、近年はゆるやかな増減を繰り返しながら200万人前後で推移しています。
生活保護を受給している人のうち、どれくらいの割合が就労支援を利用しているかというデータはありませんが、受給者の約半数は就労について何らかの支援を併用しているといわれています。
なお、生活保護と就労支援の併用には一定の条件が必要になります。
次の項で、詳しくみていきましょう。
就労移行支援と生活保護の併用は可能?
繰り返しになりますが、就労移行支援と生活保護は併用できます。
併用できる条件と、利用までの一般的な流れ、注意点をまとめました。
併用できる条件
生活保護と就労以降支援を併用するには、以下の4つの条件すべてを満たしている必要があります。
1. 世帯収入が最低生活費を下回っている
最低生活費は、法律で定められた最低限の生活を送るのに必要な費用のことです。
最低生活費は居住地、世帯人数と世帯の年齢構成によって変動するため、自治体に確認が必要になります。
東京都では単身者で月額10〜13万円程度が目安とされています。
2. やむを得ない事情で働けない
生活保護の受給は「働きたくても働けない」状態であることを、第三者によって証明してもらう必要があります。
病気やケガの場合は医師の診断書、障がいのある方は障がい者手帳や、医師かそれに準ずる立場の人による証明書を提出します。
3. 家族・親族からの援助が受けられない
家族・親族から生活費の援助が受けられる場合は、生活保護よりも援助が優先されます。
4. 資産を保有していない
土地・家屋、預貯金などの資産がある場合、売却して生活費に充当することが生活保護よりも優先されます。
原則として車も保有は認められません。しかし例外として、公共交通機関が少ない地域や車がないと日常生活を送るのが難しい、子供の送迎に不可欠であるというケースでは車を保有したまま生活保護を申請できる場合もあります。
エアコン、ストーブ、冷蔵庫、電子レンジといった生活に必要な家電は「生活必需品」なので保有したまま生活保護を申請できます。
利用開始までの基本的な流れ
生活保護受給と就労支援を併用したい場合、一般的にはまず生活保護の申請を行うことになります。
生活保護の申請は、住んでいる地域の福祉事務所が担当しています。生活保護担当の窓口があるので、相談してみましょう。
福祉事務所では、今の経済状況、就労の有無などをヒアリングして、生活保護が必要かどうかの確認が行われます。
ヒアリング後、生活保護の申請書を提出します。
福祉事務所は、申請書に書かれた内容に基づいて次のような調査を開始します。
・家庭訪問(生活状況の調査)
・資産調査(預貯金、不動産、保険など)
・働ける状態かどうかの調査
・家族や親族が援助できるかどうかの調査
これらの調査内容を総合的に判断して、支給の可否が決定されます。
なお、生活保護支給についての回答は、原則として申請してから14日以内に行われます。
就労移行支援を利用する際の注意点:自己負担額について
生活保護を受給している場合、就労移行支援の利用料は無料になります。
就労移行支援の自己負担額は、所得ごとに区分があり金額が決められています。生活保護を受給している場合、もしくは区分「低所得」の市町村民税非課税世帯は、利用料が無料です。
しかし、利用料が0円でも、交通費や昼食代などの実費は原則として自己負担となるので注意が必要です。
就労移行支援を利用する際の注意点:生活保護では障害年金=収入となる
生活保護を受給していても、障害年金を申請することはできます。
しかし、障害年金は生活保護において収入とみなされるため、障害年金の支給額は生活保護から減額されることになります。
また、障害年金の支給額が生活保護を上回った場合、生活保護の受給は終了します。
受給者が知っておきたいポイント(勤労控除・収入認定)
就労支援の利用は、自立した生活のための大きな一歩です。
生活保護を受給することで、より安定した状態でスキルを身につけたり、トレーニングを行ったりしやすくなるでしょう。
生活保護を受給しながら就労支援を利用する場合、知っておくと役立つポイントが2つあります。
生活保護受給者の就労支援サービスの利用は無料ですが、交通費などは原則自己負担となります。
しかし、社会保険料、税金、交通費は「必要経費」として、収入認定時に控除されます。
勤労のための被服費や教養費なども、必要経費として控除の対象になります。
これを「勤労控除」といいます。働いて得たお金がなるべく手元に残るようにすることで、就労への意欲を高める仕組みになっています。
なお、「収入認定」とは、受給者の得る金銭(給与、年金、仕送りなど)を生活保護費から差し引く計算のことです。
受給者が就労支援を受ける場合の流れ
生活保護と就労支援は併用することで、より安定した状態で自立へ向かいやすくなります。
スムーズにサービスが受けられるよう、就労支援と制度利用の流れについて、かんたんにおさらいしておきましょう。
就労支援とは?
就労支援、就労移行支援とは、障がいや病気によって就労が困難な方をサポートする制度です。
就労するために必要なスキルの習得、訓練を行うほか、就労後も継続的に働けるよう支えていきます。
就労支援の流れ
まずは、「見学」からスタートします。
実際に事業所を見学したり、現状を相談したりすることが就労への第一歩となります。
本格的に利用する前に、一ヶ月程度のお試し期間である「体験」が設けられています。この期間に事業所との相性や、この環境で頑張れるかどうかといった部分をチェックすることができます。
体験期間と前後して、支援内容の説明があります。この事業所で頑張れると感じたら「利用申請」、「認定調査」に進みます。
自治体の障害福祉課へ利用申請を提出すると、ヒアリング調査など就労支援の利用に必要な手続きが行われます。
利用は最長2年間
就労支援は、一ヶ月程度の「体験」以外に「暫定支給」の期間があります。
暫定支給の期間は約一〜二ヶ月で、この間に改めて利用者にとって適切なサービスかどうかを見極めることができます。
それと並行して、利用者一人ひとりに合わせた個別の支援計画書が策定されます。
就労支援は、生活保護を受給していても、この計画書に沿って最長2年間利用することができます。
よくある誤解とQ&A
生活保護と就労支援について、よくある質問をまとめました。
Q:今現在、暮らしに困っています。自立するためには、生活保護と就労支援のどちらから先に相談するのがいいですか?
A:まずは、先に生活保護の申請を行うと良いでしょう。生活保護を申請するとケースワーカーとの面談を通して、就労支援が適切な状態かどうかを判断できます。
Q:車を処分しないと生活保護の受給はできないのですか?
A:自動車は原則的に「資産」とみなされます。
しかし、子どもの送迎に不可欠であるなど正当な理由があれば、車を保有したまま生活保護を申請することもできます。
担当者に相談してみましょう。
Q:就労支援のサポートを受けている間にアルバイトはできますか?
A:原則として、就労移行支援を受けながらのアルバイトは禁止されています。やむを得ない事情がある場合は許可されることもありますが、無許可でアルバイトをすると支援打ち切りのリスクがあるのでやめましょう。
隠れてアルバイトをするよりも、生活保護を申請した方が、安心して自立へのサポートを受けることができます。
まとめ:就労支援を活用して自立を目指すために
就労支援は、生活保護の受給と併用できる福祉サービスです。
どちらも、生活や就労に困難を感じている方をサポートする制度であり、無理のない方法で自立するための道筋を一緒に検討してくれる担当者がいます。
ZERO(ゼロ)では、就労支援を通じて継続的な就労を支援しています。
継続的な就労の先にある安定した生活、自立した暮らしに向けてサポートします。
気軽に相談や見学にお越しください。

就労移行と就労継続の違いとは?就労支援の種類と自分に合った選び方
2025/12/29
はじめに
就労支援には、さまざまな方法とステップがあります。
なかでも分かりにくいのが、「就労移行」と「就労継続」です。
この記事では、就労支援の全体像を分かりやすく解説し、「就労移行」と「就労継続」について違いが分かりにくい理由も含めてまとめています。
自分に合った選び方を知り、スムーズな相談へつなげましょう。
就労支援の基礎知識|就労移行支援と就労継続支援の違い
「就労支援」は、目指す就労先と契約状況によって、次の2つに分けられます。
・一般就労
・福祉的就労
一般就労は、名前の通り一般企業や公的機関に就職して労働契約を結び、働くことです。
福祉的就労は、一般的な働き方が困難な障がい者を対象とした就労形態です。
福祉的就労の場合、支援を受ける方は、労働者であると同時に、サービス利用者でもあります。そのため、一般就労では労働の裁量が企業側にあるのに対し、福祉的就労では仕事の配分が利用者の希望を優先する形で決定されます。
こうした前提の上に、「就労移行支援」と「就労継続支援A型」、「就労継続支援B型」という支援の形がそれぞれ成り立っています。
「移行」と「継続」
就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)を整理すると、次のようになります。
・就労移行支援:65歳未満で、就労を希望する人が対象。
・就労継続支援A型:65歳未満で、一般就労や継続的な就労が困難な人が対象。
・就労継続支援B型:一般就労や継続的な就労が困難な人が対象。
就労移行支援は、就労に必要なトレーニングを提案して企業就職を目指す支援です。就職の先には働くことを通じた自立があります。
就労継続支援A型は、一般就労での継続的就労は困難であっても、それぞれの特性に合った働き方を探すことを目的としています。
就労継続支援B型は、工賃制を利用することで、無理のない範囲で就労し、その継続を目指す支援です。
このように、就労移行と就労継続は目的・ゴールがそれぞれに異なっています。
就労移行支援とは|対象者・サービス内容・利用期間
就労移行支援の対象者・サービス内容・利用期間について見てみましょう。
利用条件、対象
就労移行支援の対象となるのは、身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方、発達障がいのある方、または厚生労働大臣が定める一定の疾病、いわゆる難病患者の方です。
65歳以上は原則として介護保険サービスが優先されるため、利用年齢は65歳未満に設定されています。
利用条件は、一般企業への就職を希望しており、就職が可能と見込まれていること、また、サービスを受ける時点で就労していない(離職中)ことです。
就労移行支援を受けるために障害者手帳は必須ではありません。
しかし、自治体や医師の診断を受けた上で「障がい福祉サービス受給者証」を申請する必要があります。
なお「障がい福祉サービス受給者証」の申請は、各自治体で方法が異なります。
自治体の窓口で相談するか、ZEROへご相談をお寄せください。
訓練内容(ビジネススキル、コミュニケーション、就職活動)
就労移行支援は、就職に必要なスキルを身につけて自分に合った就職先を見つけることを目的としています。
具体的な訓練内容は多岐にわたります。
挨拶やビジネスマナーといったコミュニケーションのためのトレーニング、パソコンの基本的な使い方や履歴書の書き方などを学ぶことができます。
必要であれば、基本的な読み書きも習得することが可能です。
また、その人の適性に合った職場を探す「職場探し」、安心して長期的に就労するための「定着支援」も行われます。
定着のためのサポートとして、就職後も定期的な面談が行われ、職場で困難が生じていないかなどのヒアリングをします。
利用期間は原則2年、延長の例
就労移行支援の利用期間は原則2年間です。
しかし、特定の条件を満たすことで最長1年まで利用期間を延長することができます。
そのため、利用期間は最長3年(2年+1年延長)となります。
延長するためには、自治体から「就職の見込みがある」と判断される必要があります。
内定状況や企業の実習状況などを鑑みて判断されますが、コロナ禍や災害といった特殊な条件が加味されることもあります。
就労継続支援A型とは|働き方・特徴・平均賃金
就労継続支援A型とは、就労移行支援を利用したものの一般企業で働くのが困難とされた方や、ハローワークを通じ企業での就労は少し自信が無いが、仕事には自信がありサポートがあれば働ける方などが対象となるサービスです。
就労移行支援において就労に向けたトレーニングを受けても、さまざまな特性や困難さから一般企業・公的機関への就労が難しいと判断された場合は、継続支援A型もしくはB型に移ります。
就労継続支援A型では、利用者が企業ではなく、事業所と雇用契約を結びます。
なお、A型事業所での業務は、企業から請け負っているものもあり、業務内容が一般企業とあまり変わらないケースもあります。
そのため、A型事業所で就労しながら移行支援や、その先にある一般就労をゴールとする場合もあります。
継続支援A型は、原則として、法律で定められた規定の最低賃金以上の賃金を受け取ることができます。
就労継続支援A型の主な仕事例
就労継続支援A型の仕事には、事務作業、清掃業務、軽作業、接客業、製造加工業などさまざまな種類があります。
事務作業:データ入力、書類整理、電話応対
清掃業務:オフィス、ホテルの日常清掃、窓拭き、トイレ清掃
軽作業:部品の組立、検品、仕分け、ラベル貼り
接客:カフェの接客、レジ、商品の陳列など
製造加工業:菓子、雑貨などのものづくり
これらの他、野菜の栽培や収穫、事業所が企業から請け負った介護補助業務などもあります。
これらの仕事で得られる収入は、全国平均で約7万〜10万円です。
都道府県によって定められている最低賃金に違いがあるため、働く地域によって給与は異なります。
就労継続支援B型とは|対象者・活動内容・工賃の実態
就労継続支援B型とは、年齢や体力などさまざまな事情から一般企業への就労が難しい方が対象です。
また、50歳に達している方や、障がい基礎年金1級を受給している方も対象になります。
その他、就労移行事業者などが、B型事業の利用が適切であると判断した方も対象です。
B型は利用者と事業所との間で雇用契約を結ばない就労形態です。
利用者は成果物への対価を「工賃」として受け取ります。
この働き方により、利用者はプレッシャーを感じることなく自分のペースに合わせて働くことができます。
就労継続支援B型の主な仕事例
就労継続支援B型の仕事には、軽作業、農業、PC関連、清掃業、手工芸など、さまざまな種類があります。
軽作業:部品の組立、検品、仕分け、ラベル貼り、袋詰め
製造加工業:菓子、弁当、惣菜の製造と加工
PC関連:データ入力、資料作成
清掃業務:オフィス、工場などの清掃、クリーニング業務
手工芸:木工、織物、縫製
これらの作業で得られる就労継続支援B型の工賃は、全国平均で月額23,000円です。
工賃は事業所の売上から経費を引いて利用者に支払われるため、全国で定められている最低賃金の保障対象外となっています。
工賃のみで自立をゴールとするのは厳しいと言わざるを得ませんが、報酬改定などにより年々上昇はしています。
作業を通じてパソコンやクリーニングなど専門的なスキルを身につけられる、作ったものが売れる達成感を得られる、接客で社会とのつながりを実感できるなど、収入以外に得られるメリットも大きなものです。


- 当社の特長は、施設外就労を積極的に取り入れていることです。これにより、一般企業の中での就労体験を通じて、自分の課題を発見し、実践的なスキルを身につけることができます。施設外就労は、将来的に一般就労を目指す方にとって非常に有益な経験です。 あなたの特性に合わせた仕事を選び、個別支援を通じて、一歩ずつ自信を持って就職活動に進めるよう支援いたします。