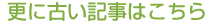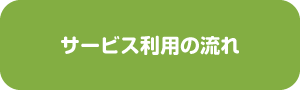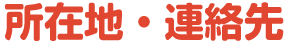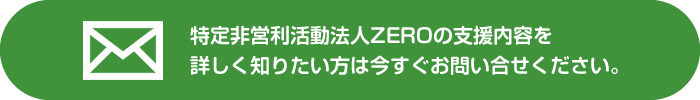就労支援を受けるには?申請手続きと利用の流れを解説
2025/07/01
はじめに
就労支援は、障害や発達特性を抱える方が仕事を「選び・始め・続ける」ための重要なサポートです。
長野県で就労支援を行うZEROでは、仕事をどのように選ぶとよいか、無理のない始め方はどのようなものか、そして継続するために必要なサポートは何か、という3つにポイントを分けて、包括的な支援を行っています。
特にADHD(注意欠如・多動性障害)の方には、集中困難や計画性の課題を補う支援があり、キャリア実現の強い味方となるでしょう。本ブログでは、就労支援申請から利用、就職後の定着までの流れを、ADHDの視点も踏まえて徹底解説します。
就労支援とは?サービス種類とADHDにいきる支援内容
就労支援は、障害者の方が自身の状況に適した職場環境で働くために、必要なスキルや自信を身につける手助けを行うものです。
ZEROでは、就労移行支援、就労継続支援B型それぞれに合わせた支援を実施しています。
就労移行支援/就労継続支援A型・B型の違い
3つの支援を理解することで、自分に合ったサポートが見つかります。
自分に必要な支援がどれか分からない場合は、まず支援の形についても一緒に考えていきましょう。
就労移行支援
就労移行支援は、一般企業への就労を目指す方を対象にした支援です。
ZEROでは、個別支援を実施することで実現する、施設外就労を積極的に取り入れています。
施設外就労は、ご自身の特性を理解すること、実践的なスキルを身につけて自信をつけることにつながっていくはずです。
就労継続支援A型
就労継続支援A型は、雇用契約を結び、給与を得ながら働ける環境を提供します。
A型は、一定の業務遂行能力が必要な場合がありますが、無理のないようにB型で就労体験を積むことも可能です。
A型が難しい場合は、無理なく就労体験の積み重ねができるB型が良いでしょう。
就労継続支援B型
就労継続支援B型では、雇用契約を結ばず、工賃制で働くことができます。
自立への第一歩として、働くリズムを体験することができる仕組みになっています。
働いたことがない方や、自分のペースで少しずつ就労を目指したい人に向いています。
ZEROでは簡単な作業を、負担の少ない短時間で行いながら、スキルアップを目指しています。
施設内就労としては「Tシャツの仕上げ作業」、施設外就労としてはカタログやダイレクトメールの「封入作業」があります。
いずれも、集中力や継続力、効率化に向けた段取りの構築といったスキルが身につけられる作業です。
ADHDに合う支援とは?支援の具体例
就労支援の中には、特にADHDに特化した支援内容もあります。
ご自身の性格や特性を理解し、適切な支援を受けることで、無理なく継続して就労できるようになるでしょう。
集中支援
短時間の集中プログラムやタスクボード、タイマーを活用して集中力の向上を図ります。
企業実習
現場で合理的配慮を受けながら実習を行い、マニュアルを活用した業務遂行や定期的な面談を実施します。
コミュニケーション強化
就労する上で発生するさまざまな対応、対話を実際に確認しながら社会スキルの向上をサポートします。
就労支援を利用開始するための流れ|申請から体験利用まで
就労支援を受けるためには、受給者証が必要です。
また、支援を開始する前に見学、体験をして、ご自身に合った支援を受けることができるかをチェックするのも重要です。
受給者証の申請方法、見学の時に確認しておくべきポイントを、利用開始までの流れに沿ってご紹介します。
問い合わせをしましょう
「どのような事業所が合っているか」という点については、その方の特性や職歴によって異なります。
まず問い合わせをして、見学や体験利用の予定を組みましょう。
不安なことがあれば、まず問い合わせの段階で質問や相談をするのもおすすめです。
見学・体験利用をしましょう
見学は事業所にもよりますが、3日間であったり、一週間であったりと様々です。
体験利用では、プログラムの一部を受けたり、1日の流れを実際に経験することができたりします。
できれば見学だけでなく、体験利用をしてみましょう。
ZEROでは、「一ヶ月間」のお試し期間を設けているので、事業所が合っているかどうかをじっくり検討することが可能です。
障害福祉サービスについてや、個別支援の内容についても専門のスタッフがしっかりお話します。
障害福祉サービス受給者証(受給者証)について知りましょう
実際に支援を受けるには、障害福祉サービスの利用申請、および受給者証が必要になります。
受給者証は、各種支援を受給するために必要な証明書です。
自治体から発行されるもので、正式名称を「障害福祉サービス受給者証」といいます。
自治体によって少しずつ違いがありますが、記載されていることや様式はほぼ共通で、「支給決定通知書」とともにご本人に送られます。
多くの場合、受給者証の最初のページには、氏名と障害種別、自治体名(発行元)が記載されています。
就労移行支援のページには、有効期間、月に何度利用できるのかといった「支給量」の記載があり、支援の利用料金についても、受給証で確認することができます。
受給者証取得ための申請をしましょう
受給者証を受け取るためには、まず自治体の「障害福祉窓口」、相談支援事務所に相談しましょう。
手続きには医師の意見書の添付など必要となる場合がありますが、まず窓口で相談することで、申請の手続き方法や必要書類について知ることができます。
自治体の認定調査、審査を経て利用が決定すると、ご本人の元へ「支給決定通知書」と、「受給者証」が送られてきます。
この手続きを経て、就労移行支援などの福祉サービスを受けられるようになります。
暫定支給について知りましょう
ご本人にとって適切なサービスかどうかをしっかりと判断するため、1〜 2ヶ月の「暫定支給」期間が設けられます。
これは仮の一時的な取り決めのことで、無理のないペースで就労を目指すために必要なステップです。
就労移行支援スタート!「個別支援計画」の策定へ
支給が決定すると、スタッフが一人ひとりに合わせた「個別支援計画」を作ります。
計画的にカリキュラムを実施していくことが、無理せず継続的に就労をする上ではとても重要です。
なお、就労移行支援は、受給者証が交付されてから最長2年間サービスを受けることができます。
事業所の選び方と見学・相談時のポイント
ご自身の特性を理解することで、「事業所でどのようなポイントをチェック、相談すべきか」が見えてくるでしょう。
例えば、ADHDの場合は、カリキュラムの柔軟性やスタッフの理解度を確認しておくことが、就労の継続にもつながります。
ADHDへの就労支援
ADHD(注意欠陥・多動性障害)の方の場合、さまざまなものに興味関心をもつことができ、アイデアを出す、行動するといったことが得意な一方、スケジュール管理が難しかったり忘れ物やミスが多くなりやすかったりする傾向にあります。
そのため、ルールやミスを減らすための取り組みを一緒に考えられる事業所が向いています。
具体的には、集中する時間を短時間に区切る、タスクを分割して、過集中をうまくコントロールするといったことが挙げられます。
見学の際は、相談してみましょう。
ASDへの就労支援
ASD(自閉スペクトラム症)の方は、ルールや手順が明確になっている作業や仕事に集中して取り組むことができます。
その一方で、臨機応変な対応を求められたり、積極的なコミュニケーションが発生したりする職場ではとまどってしまう場面が目立つことがあります。
コミュニケーション訓練や、社会スキルの獲得を目指したトレーニングを行うことで、特性を活かして就労しやすくなります。
見学・相談では、どのような訓練を実施しているのかをチェックすると良いでしょう。
就労定着支援も重要!
就労定着支援とは、就労後も長く働き続けられるように事業所がサポートを行うことです。
ZEROでは、支援制度ができる前から「就労しておわり」ではなく「いかに安心して継続的に就労できるか」を重要視してきました。
企業訪問を定期的に行い、実際に職場で安心して働けているかどうかを確認する活動をしています。
支援を受けているご本人だけでなく、企業、ご家族の皆様と連携してサポートを継続することで、はじめて「就労支援」は完結すると言っても言い過ぎではありません。
複数の事業所を見学する際は、就労後の支援についても質問しておくことをおすすめします。
自分に合った環境探しをサポートします
ADHDやASDは、子どもの時に診断を受けた方もいれば、大人になってから診断されたという方もいます。
さらに、大人になってから診断を受けた方の多くは、職場での困難さでストレスを感じて受診したというケースが多く見られます。
特に、ADHDの方は計画を立てたり複雑な人間関係を維持したりすることに難しさを感じるため、職場でミスが重なってしまうことも少なくありません。
就労する上では、ADHD、ASDといった特性に合った職場環境、業務内容を理解して、それぞれが仕事をしやすい場所を探すことが大切です。一度は就職したけれどうまくいかなかった、学生生活で困難に直面し、就職の機会を得られなかった、転職が怖い、など理由は人の数だけあるでしょう。
ZEROは、「ADHDの人はこの内容」と決めつけるのではなく、その人の特性とこれまでの生活に合った個別の支援計画を立てることで、継続的な支援を実現する事業所です。
まずは相談・見学から、就労への第一歩を踏み出してみませんか?
まとめ|就労支援活用の成功の鍵とは
就労支援は、特性をもっている方が安心して職場に通い、継続的に働くためのサポートです。
ZEROでは、相談・見学にお越しいただいた方へ、申請の流れや必要書類についても適切なフォローを行なっています。
お一人、ご家族で悩まず、お気軽にご相談ください。

ADHD特性を活かした仕事選びと就労支援活用成功法則
2025/05/29
はじめに
ADHD(注意欠如多動性障害)は、発達障害のひとつです。
「Attention-Deficit Hyperactivity Disorder」の頭文字をとった名称が使われています。
ADHDの方が直面する職場での困難はさまざまですが、適切な職業選びと職場環境の工夫により、特性を活かして働くことが可能になります。
長野県で就労支援を行うZEROでは、就労移行支援サービスの活用や、ADHDの方が働きやすい社会の実現について皆さんと一緒に考えています。
今月のブログでは、ADHDの特徴、職場での影響、職業選びのポイント、求められる企業の配慮についてまとめました。
ADHD(注意欠如多動性障害)の特徴
ADHDは、「注意力の散漫さ」、「集中の難しさ」、「多動性」、「衝動性」を特徴とします。
順序立てて行動することや、じっと待つこと、衝動的な行動を抑えることが難しく、日常生活で苦労することがあります。
なかには、うつ病や双極性障害、不安症、自閉スペクトラム症を伴っているケースも少なくありません。
ADHDのこうした特性は、職場においてもさまざまな形で現れます。
例えば、集中力が続かずタスクの遂行に時間がかかる、コミュニケーションがうまくいかずパニックに陥ってしまうといったことがあります。
しかし適切な理解とサポートがあれば、こうした特徴を改善し、個人の強みとして活かすこともできます。
ADHDは特性の現れ方によって3つのタイプに分けられます。
まずご自身のタイプを知ることで、特性を活かす職場を探しやすくなるでしょう。
不注意優位型
不注意優位型は、物事に集中して取り組むのが難しい型のことです。
不注意によるミスで作業に時間がかかったり、与えられた順番通りに物事をこなすのに困難を感じる方が当てはまります。
多動性・衝動性優位型
多動性・衝動性優位型は、落ち着いて机に向かうことに困難を感じる型のことです。
机に座ってじっとしていなければならないシーンでも、手足を絶えず動かすという特徴もみられます。
カッとなると暴力に訴えたり、順番を待てずに割り込んだりすることもあるため、「身勝手」というレッテルを貼られてしまうこともあります。
混合型
不注意優位型と多動性・衝動性優勢型の特徴を併せ持っているタイプが、この混合型です。
一般的に、ADHDと診断された方のおよそ7割は、この混合型に当てはまるといわれています。
ADHDの職場での影響:課題と改善例
職場におけるADHDの影響としては、ミスの増加やコミュニケーションの齟齬(そご)が挙げられます。
他者とのコミュニケーションや細部への注意が求められる場面で、特性が課題となることがあります。
しかし、クリエイティブなアイデアを生み出す能力や迅速な反応力といった長所も持ち合わせているため、適切な職場環境では大いに活躍することが可能です。
ADHDの方が直面しがちな困難さと、その改善例をケーススタディとして見てみましょう。
具体例1:期限管理の難しさをタスクボードで改善
営業職のAさんは、優先順位をつけるのが苦手でした。
複数案件を同時に進める際、締め切り直前まで手を付けることができず、残業が常態化していたのです。
改善するため、タスクを一覧化するボードを導入し、上司と毎朝5分確認する仕組みを整えたところ、遅延を大幅に減らすことができました。
具体例2:過集中による体調悪化を、声かけとアラームで改善
Bさんは開発部に勤務しています。
興味のあるプログラムに取り組むと周囲が見えなくなり、食事や休憩を忘れて何時間も席を離れないことがありました。
そこで、定期的に立ち上がるアラームをPCに設定、チームで声を掛け合うルールを作りました。
この配慮により、業務効率を維持しながら健康面のリスクを軽減できるようになりました。
具体例3:口頭指示の聞き漏れを、イヤフォンマイクで改善
Cさんはコールセンターに勤務しています。
口頭で複数の依頼を受けるのが苦手で、業務が立て込むと一部の指示を聞き漏らしてしまうことがありました。
そこで、本人の希望をヒアリングしてイヤフォンマイクを導入、さらに指示をリアルタイムにメモへ転送できるソフトを導入しました。
この対処により、エラー率は月平均で半分以下になり、集中して業務に取り組めるようになりました。
具体例4:感情のコントロールの難しさを、研修と休憩で改善
Dさんは、接客業に従事しています。
業務中、突然の予定変更やクレーム対応時に感情が高ぶって、声が大きくなる傾向がありました。
これを改善するため、同僚とのロールプレイ研修を実施、さらに感情が揺れた際に休憩スペースへ移動できるルールを整備しました。
この改善策のおかげで、Dさんのストレスを軽減できただけでなく、顧客満足度の低下も防ぐことができました。
これらの事例は、環境調整やチームの理解があればADHDの特性を弱点ではなく強みへ転換できる可能性を示すものです。
ご本人が困難さを言語化し、周囲が具体的なサポート策を共有することで、生産性と心理的安全性の双方を高めることができます。
ADHDの特性に適した職業選びのポイント
職業選びの際には、ADHDの特性を考慮することが重要です。自分の強みを活かせる職場であれば、能力を最大限引き出すことができるでしょう。
ADHDの方には、好きなことへの高い集中力や独創的な発想、フットワークの軽さといった強みがあります。
特性を活かせる代表的な職業を三つ挙げ、適性ポイントをまとめました。
グラフィックデザイナー
視覚的なアイデアを形にする仕事では、「ひらめき」が価値になります。
短期案件も多く、集中の波を活かしやすい点もメリットになるでしょう。
進行管理や修正履歴は専用ソフトで補助するといった対策を講じることで、発想にエネルギーを注ぎやすくなります。
営業職
顧客の課題を聞き取り、解決策を提案する業務は、即応力とコミュニケーション力が鍵です。エネルギッシュなトークや瞬時の状況判断が成果につながりやすく、数字で評価が可視化されるためモチベーションも保ちやすい職種といえます。
エンジニア/プログラマー
プログラミングやシステム構築に関心のある方は、過集中がプラスに働き、短時間で高いアウトプットを出せる可能性があります。
在宅で仕事ができる企業も多く、刺激の強さを自分で調整しやすい点も魅力です。
ADHDの特性から避けた方が良いとされる職業とその特徴
ADHDの特性は、アイデアやスピードが求められ、工程管理がツール化されている仕事のほうが適性を伸ばしやすいといえます。
一方で、成果よりも過程が評価される職場や、繰り返し作業が多い職場、細かいルールに従う必要がある職業は、避けた方が良いとされます。
例えば、工場のライン作業やルーティンワークが多い事務職は、集中力を持続させることが難しいため、大きなストレスの原因となることがあります。
ADHDの方が活躍できる職場環境と企業の配慮
企業がADHDへの理解を深め、その特性を尊重した環境を作ることは、双方にとって大きなメリットです。柔軟な勤務体制や集中できる作業環境の提供、あるいはサポート制度の充実が、その一例です。
これらの配慮によって、ADHDの方は自分の力を最大限発揮し、企業は創造性と多様性を活かした成果を得ることができるのです。
ADHDの方が特性を活かして働ける企業や、適切なサポート体制を整えている企業を探すのは、難しいことかもしれません。
そんな時は、就労支援を活用してみてください。
就労移行支援サービスの内容と活用法
ZEROでは、ADHDの方が職場に適応し、活躍できるようにするための就労移行支援サービスを実施しています。
就労支援は、ADHDをはじめとしたさまざまな障害を持つ人の、生活しやすさや働きやすさを共に考えていくというサービスです。
支援内容や方向性を見極める「相談」
就労支援は、まず相談からスタートします。
必要があれば、ご本人だけでなくご家族や周囲の方にもヒアリングしながら、その人にとってどのような職場が適しているのかを検討します。
ご本人と一緒にそれぞれに合わせた個別の支援計画書を策定し、それに基づいて行動します。
働くイメージを具体化する「見学と実習」
実際に職場見学をしたり、実習やグループワークを行ったりして、「働くイメージ」を積み重ねていきます。
応募書類の確認や面接の練習といった、就職活動に関わる支援も受けることができます。
ADHDの方の特性に合わせて、ミスを防ぐ方法や、コミュニケーションの実例といったテクニックを学ぶことも可能です。
長く働き続けるための「定着支援」
ZEROは、長く働き続けるための「就労定着支援」にも力を入れています。
ADHDの場合、特性によって仕事が長続きしない方も少なくありません。
数ヶ月で退職を繰り返していると、ご本人にとってのストレスが大きくなるだけでなく、キャリア形成にも支障が生じてしまうリスクがあります。
ZEROでは、カウンセリングを継続的に実施することで、精神的サポートをしっかりと行い、長く働き続けるための仕組みを作っています。
まとめ|ADHDの人が働きやすい社会の実現に必要なサポートとは?
ADHDの方が働きやすい社会を実現するためには、障害への理解と支援体制の充実が不可欠です。
ZEROは、個々の特性に寄り添う姿勢と柔軟な制度の整備により、各個人が自分らしく活躍できる環境が構築されることを願っています。
「仕事が長続きしない」、「周囲とのコミュニケーションがうまくいかない」といった就労の悩みを持つADHDの方は、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
ZEROは、あなたに合った働き方を一緒に探していきます。


- 当社の特長は、施設外就労を積極的に取り入れていることです。これにより、一般企業の中での就労体験を通じて、自分の課題を発見し、実践的なスキルを身につけることができます。施設外就労は、将来的に一般就労を目指す方にとって非常に有益な経験です。 あなたの特性に合わせた仕事を選び、個別支援を通じて、一歩ずつ自信を持って就職活動に進めるよう支援いたします。