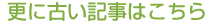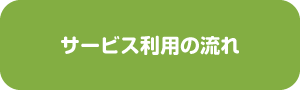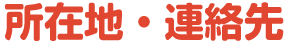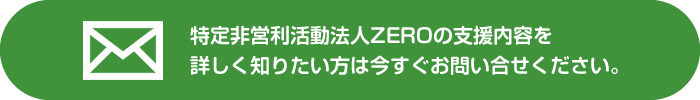就労支援の受給者証とは?申請方法と取得の流れ
2025/12/01
はじめに
受給者証は、「就労移行支援を利用するための許可証」です。
就労移行支援は誰もが受けられるサービスではありません。
市区町村の自治体が発行する「受給者証」を発行してもらうことで、初めて受けられるようになります。
今回は、「受給者証」にどのような役割があるのか、そして受け取るためにどのような手続きが必要か、について順番に紹介します。
受給者証の基礎知識 — 利用できるサービスと対象者
まずは、受給者証の基本をおさえておきましょう。
利用できる福祉サービスと、対象となるケースについてまとめました。
なお、受給者証は正式名称を「障害福祉サービス受給者証」といいますが、この記事では分かりやすく「受給者証」と表記します。
受給者証で利用できる障害福祉サービス
就労支援をはじめとする福祉サービスは、費用の一部あるいは全額が公費負担でまかなわれています。
必要とする人が正しく適切なサービスを利用できるよう、受給者証が使われています。
受給者証で利用できる福祉サービスには次のようなものがあります。
・就労移行支援
・就労定着支援
・就労継続支援A型(雇用型)
・就労継続支援B型(非雇用型)
・自立訓練(機能訓練/生活訓練)
・自立生活援助
・共同生活援助(グループホーム)
これらは「訓練等給付」に分類される福祉サービスです。
他にも「介護給付」に分類される居宅介護(ホームヘルプサービス)や、短期入所(ショートステイ)、訪問介護、生活介護などのサービスがあります。
訓練等給付は、就労や自立をサポートするための訓練、サービスが中心です。
一方で、介護給付は日常の生活をサポートするためのサービスが中心になっています。
対象となる障害・難病と支給要件のポイント
障害福祉サービス受給者証の申請ができるのは、次の条件に当てはまる方です。
・身体障害のある方
・知的障害のある方
・精神障害のある方
・障がい者総合支援法の対象となる難病と診断された方
・療育の必要性が認められた障害児の方
医師の診断書および意見書、児童相談所の判断によってこれらの条件に当てはまるとされる方は、受給者証の申請ができます。
この場合、障害者手帳を持っていなくても、診断書や意見書があれば、申請をすることができます。
ただし、自治体によっては利用サービスごとに細かい規定が設けられている場合があるので、申請の際に確認は必要です。
申請の流れ — 必要書類から発行までのステップ
申請と手続きは、自治体によって少しずつ違いがあります。
そのため、ここではZEROのある長野県を例として必要なステップを見ていきましょう。
実際に申請をする際は、住んでいる自治体の窓口にあらかじめ確認するようにしてください。
相談窓口の使い方と申請手続きの進め方
長野県では、各市町村の窓口で手続きを行います。
そのため、まずは就労移行支援を利用したい旨を自治体の「障害福祉窓口」や「相談支援事務所」に相談するところからスタートしましょう。
申請に必要な診断書・意見書・各種書類
申請には、次のものが必要になります。
・主治医の診断書/意見書
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
その他、印鑑、障害の状態が確認できる書類や、保健福祉センター所長が必要と認める書類など、自治体によって追加の持ち物が定められている場合もあります。
また、障害者手帳をすでに持っている場合は、手帳を持参する必要があります。
持ち物について心配な場合は、まず相談窓口やZEROのようなサポート窓口へお問い合わせください。
申請〜審査〜受給者証支給の流れ
申請〜審査〜受給者証支給までは、1〜2ヶ月前後かかります。
市区町村の状況によっては、さらに長い時間がかかることもあり、最初のうちは「暫定支給」となることもあります。
順番にみていきましょう。
申請すると、まず就労移行支援などのサービスを受けるのに適しているか、認定調査が行われます。
認定調査とは、実際の生活状況を自治体の職員がヒアリングすることです。
審査が完了すると、調査に基づきサービス等利用計画案が作成されます。
この計画案は、どのように支援を利用するかという具体的な方法を盛り込んだもので、申請者本人が作成することもあれば、指定特定相談支援事業者が作成することもあります。
自治体によっては、本決定の前に2ヶ月ほど「暫定支給」が行われることもあります。
暫定期間は、実際に就労移行支援を利用しながら、福祉サービスの利用が妥当かどうかを判断するために設けられています。
サービス利用が「本決定」となると、自治体から申請者本人の元へ通知書と受給証が送られてきます。
受給者証を受け取ったら、就労移行支援事務所と正式に契約を結び、利用を開始することができます。
受給証の更新について
受給者証は一度取得すれば良いというわけではありません。
有効期限が決まっていて、それを超えてサービスを利用したい場合は更新手続きが必要です。更新手続きは、期限の1〜3ヶ月前から行えるのが一般的で、期限が近くなると自治体から更新のお知らせが届くようになっています。
更新のお知らせを受け取った時に利用を延長したい場合は、忘れず早めに手続きを行うようにしましょう。
ちなみに期限切れを更新せずにいた場合は、改めて行った申請が受理されるまで就労移行支援などのサービスが一時的に利用できなくなるケースがほとんどです。
継続的な支援を受けられるように、更新手続きは早めに行いましょう。
受給者証で利用できる就労支援と事業所の選び方
受給者証を受け取ったら、自分に合った就労支援を受けることができます。
最適な事業所選びができるよう、就労移行・A型・B型・定着支援の違いと、事業所を選ぶ時の見学のポイントについてみてみましょう。
就労移行・A型・B型・定着支援の違い
受給者証で利用できる就労支援などの福祉サービスには、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援という種類があります。
就労移行支援は、一般就労を希望する方をサポートするサービスです。一般企業への就職を目指す方が利用します。
就労継続支援A型は、一般企業への就職に困難を感じる方をサポートするサービスです。
働く場所の提供と、スキル向上のための訓練を実施します。
B型は、一般企業やA型での就労が難しい方を支援するためのサービスです。
A型では雇用契約が結ばれるため賃金が発生します。
B型では雇用契約を結びませんが、工賃という形で労働の対価が支払われます。
例えば、雇用契約にとらわれず社会と接点をもつことからスタートしたい場合は、B型から始めます。
就労定着支援は、就職した後の定着をサポートするサービスです。
一般企業に就職した障害のある方を対象としたサービスで、一つの企業で長く働けるよう課題解決に一緒に取り組んだり、企業との調整を行います。
自分に合う事業所を選ぶための視点と見学のポイント
自分に合った支援を受けるには、事業所選びも重要です。
見学をして、適した支援が受けられるかどうかをよくみてみましょう。
事業所の見学は、Webサイトの問い合わせ窓口から申し込むのが一般的ですが、電話、チャットから申し込みできる事業所もあります。
見学では、事業所のスタッフに気になる点を質問することもできるので、心配なことや不安なことは質問してみてください。
見学後は、本当にその事業所が自分に合っているかどうか「体験」を通して確認することもできます。体験では訓練プログラムを受けたり、一日の流れを実際に行ったりすることで、「自分が就労支援を受けるイメージ」を描きやすくなります。
見学・体験では、分からないことやもやもやしていることをなるべくスタッフと共有するようにしてみてください。
不安なことを共有することで、支援を受けやすくなり自分に合っている事業所を見極めやすくなるはずです。
受給者証のよくある質問集
ここまでの復習として受給者証の申請と就労支援の利用について、よくある質問をまとめました。
Q:障害者手帳がないと受給者証の申請はできないのですか?
A:障害者手帳がなくても、受給者証の申請はできます。医師の診断書・意見書など障害の状態が分かる書類があれば申請が可能です。
Q:受給者証は申請からどれくらいで支給されますか?
A:自治体によって違いはありますが、およそ1〜2ヶ月前後です。市区町村によっては正式な発行前に2ヶ月ほど「暫定支給」期間が設けられることがあります。
Q:申請はどのタイミングで行ったらいいですか?
A:一般的に、利用したい就労移行支援事業所を決めた段階で申請することが多いようです。事業所が決まれば、スタッフから詳しい説明を受けることができるので、申請までスムーズに行うことができます。
Q:通所予定の事業所が決まっていなくても申請はできますか?
A:申請できるかどうかは、自治体によって違いがあるのが現状です。一般的には、事業所が決まってから申請する方がスムーズとされています。
Q:申請が通らないことはありますか?
A:申請については各自治体の判断に委ねられています。ですが、もしも却下された場合は自治体に却下理由を確認することができます。また、納得できない場合は3ヶ月以内に審査請求を行うことができます。
スムーズに支給決定がなされるよう、一緒に取り組んでいきましょう。
まとめ
受給者証は、適切な就労支援を受けるために欠かせないものです。
申請から支給には1〜2ヶ月かかりますが、暫定支給などの制度を利用して適切な就労支援を受けることができます。
就労支援にはA型、B型、継続支援といったさまざまなタイプがあり、無理なく進められるぴったりの制度がきっと見つかります。
まずはZEROの窓口へ、お気軽にご相談をお寄せください。

【2025年最新】法定雇用率と達成状況の全貌
2025/10/31
はじめに
法定雇用率の段階的な引き上げ予測と、全国的な達成状況についてご存知ですか?
雇用率の達成は、ノーマライゼーションの理念に基づく共生社会の実現と深く関わっていますが、給付金制度などを活用して企業だけが頑張り過ぎないことも重要です。
就労支援と「長く、安心して働く」ためのサポートを実施しているZEEROが、2025年最新の法定雇用率を取り巻く現況について、法改正の経緯を含め包括的にお伝えします。
障害者雇用促進法の歩みと法定雇用率の変遷
障害者雇用促進法は1976年に前身となる「身体障害者雇用促進法」が制定されてから、何度も改訂を重ねて現在の形になりました。現在の形も完成形というわけではなく、時代に合わせて今後もさらなる改定が加えられていくことでしょう。
法が制定された経緯と改正の歴史について簡単にご紹介します。
「障害者雇用促進法」制定から法改正まで簡単まとめ
「障害者雇用促進法」の前進となる「身体障害者雇用促進法」は、1960年に制定されました。
日本は高度経済成長期にあり、世界各国でも障害者雇用が積極的に行われる機運が高まっていた時代です。
しかし、この法で掲げられたのはあくまで努力目標であり、対象も身体障害者のみであるなど限定的なものでした。
この「身体障害者雇用促進法」は1976年に改正されます。改正に伴い、法定雇用率の達成は努力目標でなく「義務」へと変わりました。
そして達成できない企業からは納付金を徴収するようになり、これを財源として雇用給付金制度が設けられました。雇用給付金は、障害者雇用を積極的に行う企業に対して調整金や助成金という名目で給付されるようになります。
さらに11年の時を経て、1987年に「身体障害者雇用促進法」は現在の「障害者雇用促進法」へと改名されます。
追って1998年には知的障害者が、2018年には精神障害者が「障害者雇用促進法」の適用範囲へと加わりました。
近年の改正動向:法定雇用率はCSRの指標に
改正の動向として特に注目したい数字が「法定雇用率」です。
法定雇用率は1976年から現在に至るまで、年々引き上げられてきました。
1976年10月:1.5%
1988年4月:1.6%
1998年7月:1.8%
2013年4月:2.0%
2018年4月:2.2%
2021年3月:2.3%
2024年4月:2.5%
2026年7月:2.7%(予定)
2025年現時点での法定雇用率は2.5%ですが、来年度(2026年)には2.7%に引き上げられることが決定しています。
障害のある人もそうでない人も暮らしやすい共生社会実現のため、そして人手不足解消のためにも、段階的に法定雇用率の引き上げは続いていくでしょう。
障害者雇用をCSR(Corporate Social Responsibility/企業の社会的責任)の指標として掲げる企業も増えてきており、「障害者雇用促進法」が企業の信頼性向上に寄与している側面も見逃すことはできません。
精神障害者の算定対象化と短時間労働者の扱い明確化
近年の改正動向でもう一つ注目したいのが、「算定方法」に関する部分です。
身体障害者、知的障害者を一人雇用しているとカウントされるためには、一人につき週30時間の雇用が必要ですが、精神障害者の雇用は週20時間以上で一人とカウントされます。
これは、精神障害者の職場定着を進めるために設定された特例措置ですが、当面の間継続されます。
また、以前は原則週20時間以上の常用労働者のみが算定の対象とされていましたが、現在は20時間未満であっても、0.5人としてはカウントできるようになっています。
2025年改定後の法定雇用率と今後の展望
改正の歴史を振り返ったところで未来に目を向けてみましょう。
2025年以降の引き上げスケジュールと、厚労省が発表している達成率についてみていきます。
実は、法定雇用率は事業主の区分によって違いがあります。
2025年10月時点で、それぞれの区分別の法定雇用率は次のようになっています。
民間企業:2.5%
都道府県の教育委員会:2.7%
国・地方公共団体:2.8%
先に挙げたように、2026年7月には民間企業の法定雇用率が2.7%に引き上げられます。
また、今後は2030年に向けて3.0%程度に引き上げが続くのではないかという予測もあり、現在は達成率ギリギリの雇用状態である場合、今後に向けてさらに障害者雇用を拡大していく必要があります。
引き上げを見越して企業戦略を構築していきましょう。
厚労省による達成状況データ
法定雇用率に関する厚労省発表データは、2024年のものが最新です。
「障害者雇用状況の集計結果」では、雇用障害者数は過去最高を更新しているものの、法定雇用率達成企業の割合は46.0%と、対前年比で4.1ポイント低下する結果になっています。
このデータからは雇用数自体は増えているものの、達成率の引き上げに追いついていないという現状がみてとれます。
障害別のデータでは、精神障害者の雇用者数がもっとも伸び率が大きく、改正によって算定方法が変化したことが雇用を後押ししていることが分かります。
身体障害者の雇用者:36万8,949.0人(対前年比2.4%増)
知的障害者の雇用者:15万7,795.5人(対前年比4.0%増)
精神障害者の雇用者:15万717.0人(対前年比15.7%増)
※参照資料「厚生労働省 令和6年 障害者雇用状況の集計結果」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html
法定雇用率未達成によるリスク
2024年の未達成企業は、6万3,364社でした。
しかし、その過半数である64.1%が0.5人ないし1人が不足している企業であり雇用に向けて積極的に努力をしている企業が大半であることが窺えます。
一方で、一人も障害者を雇用していないいわゆる0人雇用企業も3万6,485社あります。
障害者雇用の義務を怠ると、状況報告書の提出や行政指導・改善勧告の対象になります。また悪質な場合は企業名が厚労省のサイトで公開されるため、ブランドイメージ低下が決定的なものとなってしまいます。
雇用率達成のための土壌づくり
障害者の雇用率を達成するためには、企業のソフト面とハード面のアップデートが必要です。
障害者雇用は特別なことから、当たり前のことになりつつあります。
障害の有無に関わらず、互いに支え合う社会を目指すことをノーマライゼーションといいますが、この理念を理解することがアップデートの第一歩となります。
採用プロセスや人材開発プログラムの見直しをするとともに、働く人たちにノーマライゼーションの理念を共有してもらい、職場に理解を深めることが「ソフト面」の整備には欠かせません。
ハード面では、支援機関との連携や現場の具体的な受け入れ体制づくりが重要になります。
これについては、厚労省が給付金制度などを整えているため、支援を活用しながら働きやすい環境を構築していくと良いでしょう。
法定雇用率を達成するために役立つ企業支援策
法定雇用率が引き上げられると、その達成が難しいと考える事業主も増えてきます。
厚労省は雇用率達成のために障害者雇用調整助成金、職場定着支援、ジョブコーチ派遣、設備改善助成金といった支援策を用意しているので、上手に活用して達成を目指すと良いでしょう。
企業支援策:障害者雇用調整助成金
障害者雇用調整助成金は、雇用率以上の障害者を雇用している事業主に対する支援策です。
法定雇用率を超えた障害者数に応じて月額2万3,000〜2万9,000円が支給されます。
障害者雇用は、職場環境の整備や管理、設備の改善など経済的な負担が生じることがありますが、助成金によってこの一部を賄うことができるはずです。
企業支援策:障害者職場定着支援コース
障害者職場定着支援コースは、障害特性に合わせた雇用管理や柔軟な働き方のための措置を講じる事業主に対する支援策です。
職場定着支援計画の認定を受けた上で、通院・治療のための有給休暇付与、職場支援、中高年障害者の雇用継続支援などの必要な措置を実施すると、助成金が支給されます。
企業支援策:ジョブコーチ支援
ジョブコーチとは「職場適応援助者」のことです。
障害者の職場適応が難しい場合、ジョブコーチに出向してもらい、特性を踏まえた専門的な支援を受けることができます。
ジョブコーチには、「配置型」、「訪問型」、「企業在籍型」の3つがあります。
配置型ジョブコーチは地域障害者職業センターに配置されていて、訪問型・企業在籍型のジョブコーチと連携して必要な支援が行われるよう援助する存在です。
訪問型ジョブコーチは、厚生労働大臣が定める研修を修了した者で経験や能力が豊富です。社会福祉法人などに雇用されています。
企業在籍型ジョブコーチは、障害者を雇用する企業に雇用されるジョブコーチのことです。こちらも機構や厚生労働大臣の定める所定の研修を修了している者が活動しています。
企業支援策:設備改善助成金
設備改善助成金には、障害者作業施設設置等補助金、障害者福祉施設設置等助成金があります。これは障害者を雇用する際に、仕事がしやすいように配慮された施設を作ったり、改造したりする必要がある際に助成が受けられる制度です。
障害者雇用は「義務」から「経営戦略」へと変化!制度を活用しましょう
障害者雇用は、法定率によって「義務」とされています。
しかし、近年ではその価値観が社会的責任の履行に伴う企業のブランドイメージ向上や、信頼性向上のための戦略へと変化しつつあります。
とはいえ、障害者が働きやすい環境を新しく整備したり、配慮が行き届いた職場へアップデートしたりするのは費用と時間というコストがかかります。
実現を支援する制度を上手に活用して、無理なく進めていくのが良いでしょう。
まとめ
法定雇用率はクリアしなければならない数字ですが、達成のためには社会や企業が成熟している必要があります。
言い換えれば、あと0.5人や1人で雇用率を達成できる企業は、ノーマライゼーションの理念がほぼ浸透しており、企業としてほぼ成熟しているとみることができます。
障害のある人とない人が共に働くことは、特別なことではなく当たり前であるという理解を深めることが、段階的に引き上げられる2025年以降の達成率をクリアしていくのに必要なことではないでしょうか。


- 当社の特長は、施設外就労を積極的に取り入れていることです。これにより、一般企業の中での就労体験を通じて、自分の課題を発見し、実践的なスキルを身につけることができます。施設外就労は、将来的に一般就労を目指す方にとって非常に有益な経験です。 あなたの特性に合わせた仕事を選び、個別支援を通じて、一歩ずつ自信を持って就職活動に進めるよう支援いたします。